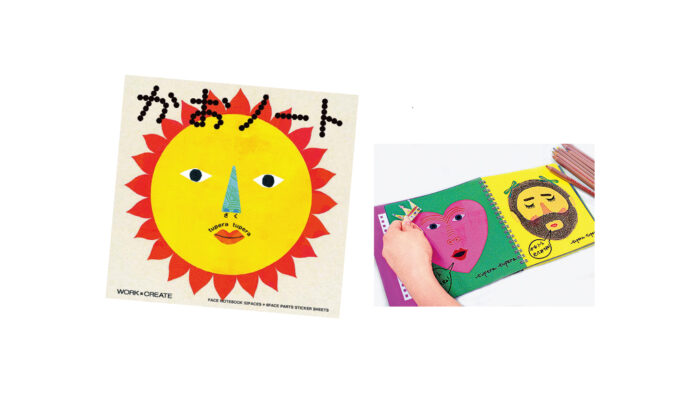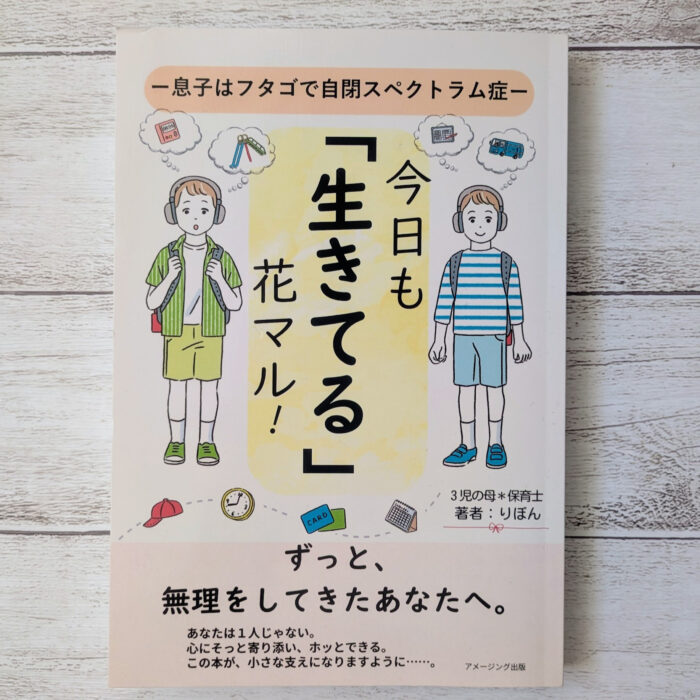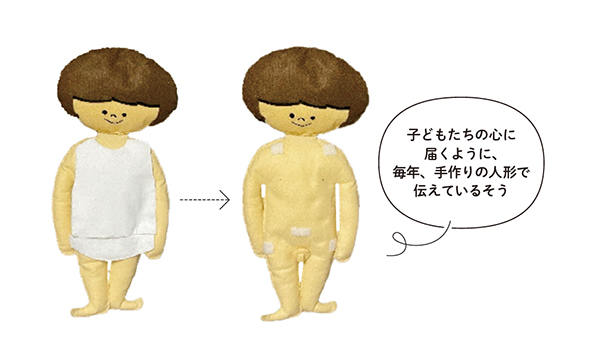更新 :
キレやすい子どもに育ってしまう親のNG行動3つ

「キレやすい子ども」「すぐにキレる子」という表現を聞くことがあると思いますが、どういう状態のことを言うのでしょうか? 「キレる」と「怒る」はどちらも不快な気持ちや不満がガマンの限界に達して起こる行動です。しかし「キレる」という場合は、その感情の高ぶりを自分では制御できず、理性を見失って行動したり言葉を発したり、時には暴力をふるったりすることを意味します。
「キレやすい子ども」にしないためには、子どもが乳幼児の段階から、かかわり方や声かけの仕方に配慮する必要があります。今回は心理カウンセラーの立場から、子どもが「キレやすくなる」親のNG行動について紹介します。
子どもが不安を訴えたときに対処をしない
いわゆる「キレる」行動の裏側にある心理として、非常に大きいのが、不安です。何か不快なことが起こったとき、どうしたらいいかがわかれば冷静に対処できますが、対処法がわからないとパニックを起こしてしまうことは大人でもあるかもしれません。子どもも、どうしたらいいかわからず不安だから、大声を出したり暴れたりすることで不安を紛らわせ、あわよくば対処してもらおうとするのです。
こうした行動の根本は、子どもが生後まもない頃の親の対応にあるとも言われています。生後すぐから、子どもは不安や不快という感情をもつと、泣くことで対処しようとします。親を呼び、不快な状態を解消してもらい、安心させてもらいたいのです。
ところが泣いてもすぐに大人が対処しないなど、不安が解消されない環境に長くいた子どもは、不安を抱えたままガマンをするしかありません。このときの経験は、将来にわたって子どもの不安感を強くし、結果的にキレやすい性格になってしまうと考えられています。
子どもが不安を解消できるよう対処して
まずは子どもの不安に向き合い、しっかり対処をして安心させるよう心がけます。
例えば友達とトラブルになった、絵がうまく描けなかった、みんなで踊るのがイヤだなど、就園以降にさまざまな不安や不満を抱える場合があります。このとき「あなたが悪いんでしょ」「そんな小さなことで落ち込まないでよ」「ワガママ言わないの」などといったかかわり方や言葉かけは、子どもの不安をますます大きくします。
子どもが不安を抱えていると感じたら、「何があったか聞く」「できていることを伝える」「うまくできるポイントを一緒に探す」など、まずは寄り添うことで、子どもの不安は解消しやすいでしょう。
怒鳴り声で子どもをコントロールしようとする
子どもが失敗したとき、親の気に入らないことをしたときなど、怒鳴ってやめさせたり、大きな声で叱ったりした経験はないでしょうか。このとき子ども自身は強い不安を感じて萎縮しますが、同時に「気に入らない時は、怒鳴ればいい」ということを学びます。体罰も同じで、親が体罰を与えていると、他人が気に入らない時は暴力で制すればいいと認識することがあります。
したがって、成長してから強い不安を感じるようになった時に、幼い頃に親からされたように、大きな声で怒鳴る、暴力をふるうといった態度に出ることがあるでしょう。

否定せずに具体的な指導で子どもを安心させましょう
子どもを怒鳴るときは、「ダメ!」「やめなさい!」あるいはこれらに類する言葉で、子どもの考えや行動を否定してしまうことが多いものです。しかし否定する言葉だけをかけられても、子どもは「じゃあ、何がいいのか」が理解できないため不安を強めていく結果となります。
したがって子どもになにかを指導するときは、常に「なぜダメで、具体的にどうしたらいいか」をセットで指導するようにします。極端な例をいえば、「ゲームをやめなさい!」と怒鳴るのはNG、その後「勉強しなさい!」という指導だけも足りません。怒鳴ることなく、ゲームをやめるよう話をした後、「ゲームはたくさんやったから、この問題集を2ページやろうか」といった提案をするのがベターです。
子どもの前でその子をけなす
案外多いのが、子どもの目の前で、その子をけなしている親です。例えば親戚の前で「うちの子は全然ダメで…」と謙遜したり、子どもに向かって「どうせあなたにはムリよ」などと言っていたら要注意。こうしたことを度々繰り返すうちに、子どもは自信を失い、毎日を不安だらけにしてしまいます。そのため成長するに従ってキレやすい子になってしまう可能性を高めるでしょう。
親があまり意識しないで言っているつもりでも、けなし言葉を付け加えていることがあるため、注意してください。例えば「これを片付けてよ。できない子だね」「早くしてって言ってるでしょう。にぶいね」など。こうしたほんのひとことのけなし言葉が子どもの自信を打ち砕いているのです。
けなさず「ほめて、感謝する」のステップを大切に
子どもをけなす言葉は、親が注意して発さないようにするしかありません。普段の自分の言動をかえりみて、該当するような言葉があれば今後言わないよう気をつけましょう。
そのうえで、ほめ言葉と感謝の言葉に置き換えていきましょう。「片付けてくれる? ありがとう」「もう、時間がぎりぎりだから早くできるかな? できたね、えらいね!」といったプラスの言葉に置き換えると、子どもが不安感を徐々に解消し、自信をつけ、キレるまえに考えるクセをつけていくでしょう。
親自身のトラウマも…自分を認めて乗り越えましょう
子どもをキレやすくするNG行動をとってしまう親は、親自身が、自分の親からNG行動をされていたことも少なくありません。昔はこうしたNG行動は普通の教育方法と考えられており、「NGである」という認識はなかなか広まらなかったのです。そのため自分がされたことをそのまま子どもにしているだけ、という親もたくさんいます。
本当は、怒鳴ったりしたくないし、もっと余裕をもって子育てをしたい、キレやすい子どもに育つのは困る…と考えていると思います。「でも自分も親に怒鳴られて育ったし」「怒鳴らないとうちの子なんにもしない」「怒鳴らない、けなさない子育てなんて自分にはムリ!」と考えているかもしれません。
もしもそう思ってしまうなら、あなた自身が不安感の中で苦しんでいる可能性があります。子どもを認めるのと一緒に、ぜひ自分自身の頑張りも認め、「私にはできる!」という思考にシフトしていきましょう。