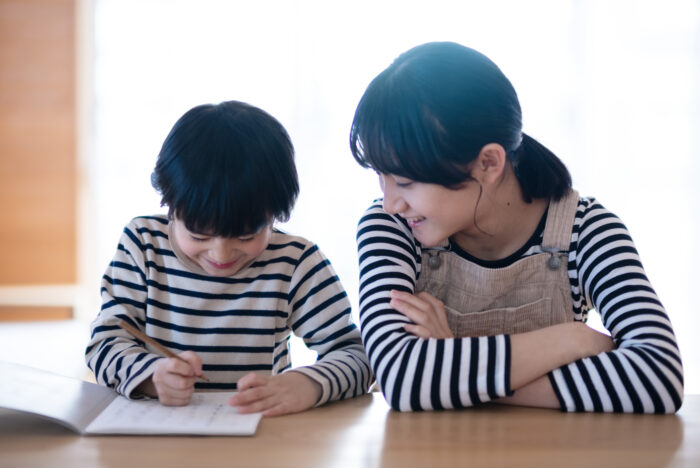担任の怒声に脅える小3の娘。学校に要望を出しても変化がありません
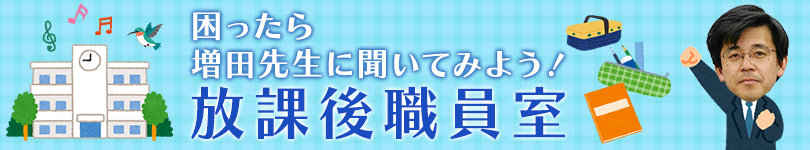
Q.前の席の男の子がよく怒鳴られるため、小3の娘が萎縮しておびえ「学校に行きたくない」と言いだしました。どう対応すればいい?
小3の女の子です。前の席の男の子がよく担任の先生から怒鳴られているそうで、その怒声におびえています。「学校に怖くて行きたくない」とも言いだしました。
学校に提出する記入式のプリントがあったので、【担任に伝えたいこと】の欄に「娘の近くで大きな声を出さないでほしい」ということを書きました。担任からは特に返答はないですが、娘へはどういった対応をすればよいでしょうか?
その先生は、昨年受け持ったクラスからも、恐くて学校へ行けなくなった女生徒が出たそうです。娘もそうですが、その女の子が怒られているわけではなく、他の生徒を怒っているのが怖いらしいです(くるぴか)
A.叱ることは大切ですが、怒って感情をはき出すのはNG

子ども達はきちんと筋が通って叱られる場合は、しっかり受けとめるものです。子ども達が怖がるということは、その教師は感情を表に出しすぎているのかもしれません。つまり「叱る」ではなく「怒る」になっているのです。
私も小学校教諭時代は子どもを叱りました。叱るときは、最初に「そういうことをしたらダメだろ!」と言ってから、どうやってその子や、クラス全体に価値観を教えるか、説得をするかということを考えながら、また一人ひとりの子どもの様子や、顔色を見ながら話を進めていきます。つまり頭のどこかで冷めた自分がいるのです。教師は教育のプロですから、感情にまかせて「怒る」のではなく、冷めた自分がいる「叱る」でなくてはいけないのです。
教育という仕事は、子ども達の社会性や価値観を育てなくてはいけないですから、「叱る」という機会は何度もありますし、必要な行為でもあります。でも、この先生の行為は「叱る」ではなく、「怒る」になってしまっています。そして、言うことを聞かない男の子がガマンできないのではないでしょうか。きっと「学級をきちんとさせたい」という思いが強く、また学級の見栄えを気にするタイプなのかもしれません。
小3という年齢は、ギャングエイジといわれ、大人の価値観から脱却し、「自分らしさ」を考え始めたり、友達との集団で何かをすることを好むようになります。また、大人の評価より友達の評価を気にするようになります。そうした特徴がありながらも、教師の価値観も色濃く反映されてしまう時期です。
教師が特定の子どもばかりを怒っていると、「あの子は、先生に怒られるダメな子なのだ」というすり込みが行われます。そして、教師と子どもの両者が「あの子はダメな子」というまなざしで見ると、本当にダメな子になってしまうのです。この教師の行為は、そうした子どもを作ることで子どもを管理しているようにも見えます。
感情に任せて過度に怒ることが、子ども達にさまざまな影響を与えているのです。特に相談者の娘さんのように、先生を怖がったり、学校に行くのがイヤになってしまうという影響もとても大きいのです。
担任や学校に「指導の方法の改善」を訴えましょう!
こうしたケースでは、娘さんに「ガマンしろ!」などと言ってはいけないです。むしろ、変わらなくてはならないのは教師の方です。
「学校に行くのが怖い」と言っているお子さんがどのくらいいるのかを確かめ、そうした父母数人で、指導の改善を訴えましょう。モンスターペアレントといわれないように、「同じ子どもを大声で怒鳴り続けることで、子どもが学校へ行くのを怖がっている」「親も教師や学校に協力するのでよい学級を創っていきたい」「過度に怒るのではない方法で指導してもらいたい」といったことを話すとよいと思います。正しい要求は、きちんとしてよいと思います。
【新刊】
新刊「『いじめ・自殺事件』の深層を考える-岩手県矢巾町『いじめ・自殺』を中心として-」(本の泉社、1620円)発売中。