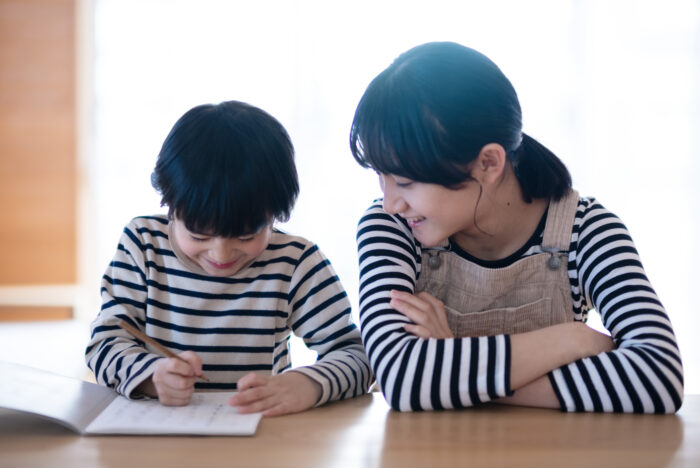更新 :
子どもを過剰に叱ってない?それは“依存”かも…抜け出すポイント3つ

子どもにイライラしてつい怒鳴ることを続けたり、感情的に叱ることがダメだとわかっているのにやめられなかったり…。そのあとに自己嫌悪に陥った経験のあるパパやママは多いのではないでしょうか。
大声で叱ることをやめられないのは、「叱ることに依存しているため」かもしれません。人の心理の働きを突き詰めると、叱るという行為には依存性があるという驚くべき事実が隠されていることが分かっているのです。
今回は心理カウンセラーの立場から、叱ることの依存性について、またそこから抜け出すための3つのポイントについてお伝えします。
叱る=気持ちがいい?叱ることが依存だと言われるようになった理由
よかれと思って子どもを叱っているだけなのに、なぜ依存だと言われなければならないのか、まずはその理由を見てみましょう。
叱ること=上下関係を明らかにする行為

叱ることは、自分と子どもの間にある上下関係を明らかにする行為です。叱った結果、子どもは「ごめんなさい」と反省の弁を述べ、この瞬間、親がそのつもりでなかったとしても、子どもとの間で勝敗がつきます。とりわけ小さな子どもが相手のとき、親は常に上の立場となって優越感を得られるわけです。
この「私の立場が上だ!」という感覚は、一種の喜びです。子どもが言うことをきかなかったとき、また思い通りに動かなかったとき、この喜びは脅かされます。親は立場を取り戻そうと、再び強く叱ってしまうのです。
例えばあなたが子どもを叱ったときに、「ごめんなさいは?」と言っているとすると、子どもを屈服させることが快感になっている可能性は高いでしょう。
上の立場として認められたいのは、親自身の自己肯定感が低いから
「子どもよりも自分が上の立場だ」と感じたい理由として非常に大きいのが、親自身の自己肯定感の低さ、満たされない承認欲求です。人は誰でも、誰かに認められたいと思っています。ほかの部分でそれが満たされている場合、わが子を叱ることで自らの立場を誇示する必要がありません。ところが日常のなかで自分の存在があやふやになっていると、自分は誰にも認められていないという悲しみとともに、叱ることによって自分の存在を知らしめたい、満たされたいという欲求に支配されてしまいます。
脳科学の分野からも研究が進んでいる
叱ることへの依存メカニズムは、現在、脳科学の分野からも研究が進んでいます。叱ることによって、ギャンブルと同じような脳の興奮状態が生じることがわかってきているのです。しかも脳が徐々に快楽に慣れることで麻痺し、さらに大きな興奮を欲するようになってくるのもギャンブルと同じです。
大きな興奮を求めるということは、些細なことでも盛大に叱りたくなっていくという状態を意味します。「前はこんなに怒らなかったのに」と考えてしまうようなら、黄色信号かもしれません。
叱ることへの依存から抜け出すポイント
では、叱ることに依存してしまっているかも…と気づいたときの対処法には、どんなものがあるでしょうか。依存から抜け出すためのポイント3つを紹介します。
パートナーと話し合い、些細なことでも褒めてもらう
まずは「自分が叱ることに依存しているかもしれない」ということを、パートナーと共有してみましょう。そしてこの状況を脱するために、普段のあなたの頑張りを褒めてもらいます。毎日家事をしていること、仕事を頑張っていることなどを認めて口にしてもらうようにしましょう。
叱ることに依存する理由のひとつは、誰も自分を見てくれていないのではないか、あるいは自分が批判されているのではないかという不安です。とりわけパートナーの目線は大切で、努力を認められることが大きな安心につながります。
日記をつけて自分を褒める
自分自身でも、自分が普段からどんなに頑張っているかを日記をつけて確認してみましょう。いざ書こうとすると、1日の反省がたくさん頭に浮かぶはずです。しかし日記に書くときは、反省のボリュームは最低限にしてください。大事なのは、自分への褒め言葉をたくさん並べること。反省点があったとしても、「でも頑張れた。私、偉かった!」ということがたくさんあるはずです。それを日記に書いて、見返すことで、自分自身のいいところを意識するクセがつくでしょう。
自分を「よくやった」と認めることのできる時間をもつ
あなた自身が充実した時間を過ごすことが大切です。子どもが小さいと“自分のための時間”はもちづらく、家事に仕事にと追われて、自分のための時間が取れない人は多いでしょう。
ぜひ調整して、自分のための時間を作ってください。趣味で何かを作る、何かを勉強する、カフェで日常の自分を振り返って頑張りをねぎらう、おいしいものを食べるなどの時間は、自己肯定感を高め、叱ることに依存する自分に陥らないために必要です。
ストレスはしっかり解消しつつ視野を広げましょう
子どもを過剰に叱ってしまう人は、実はとてもしっかりした人が多いのです。こうしなければいけない、これでなければ間違っていると考えます。子どもがそれに沿わない行動をとれば、「矯正してあげなくては、将来的に子どもが恥をかく」などと考え、子どものために“よかれと思って”叱ることになります。
ところが、あなたの「こうでなければいけない!」は、世の中ではそうでもないという場合もあります。また大人の世界とは違い、子どもに完璧を要求するのは当然ムリな話。大声で叱るのではなく、長期戦でじっくりと繰り返し言い聞かせるしかないのです。
「大声で怒鳴ったり、叱り続けることに意味はない」とあなた自身が認識するためには、視野を広げ、さまざまな人と交流をもつのが近道です。そうすることでほかの人の子育て事情にも触れつつ、ストレスも解消され、少しずつ叱ることへの依存から脱却できるのではないかと思います。
■参考文献
・「〈叱る依存〉がとまらない」著者 村中直人/出版社 紀伊国屋書店
・依存症についてもっと知りたい方へ(厚生労働省 ホームページより)