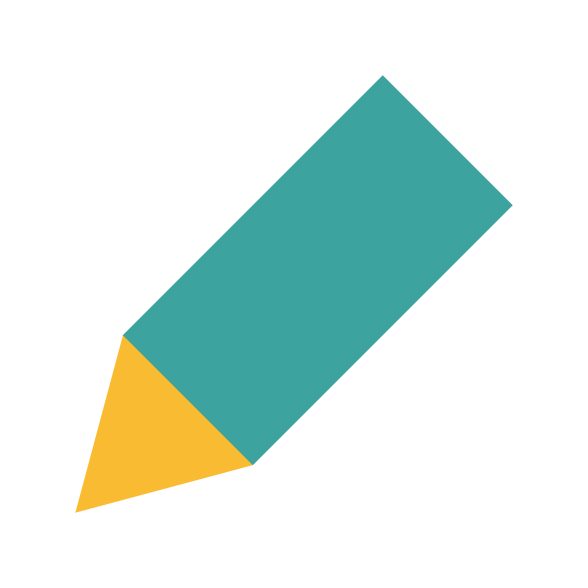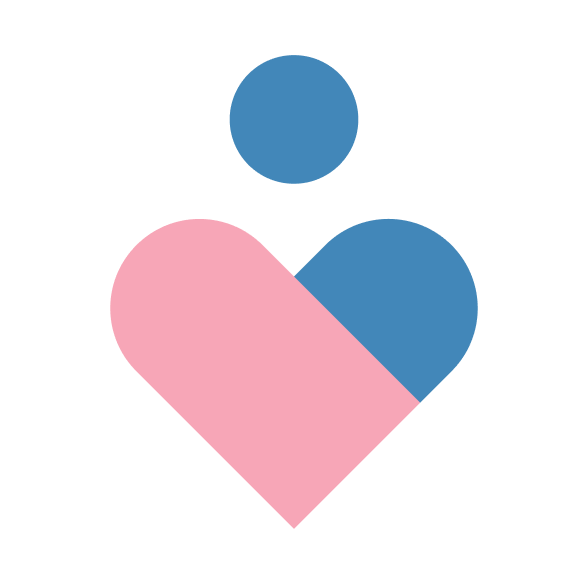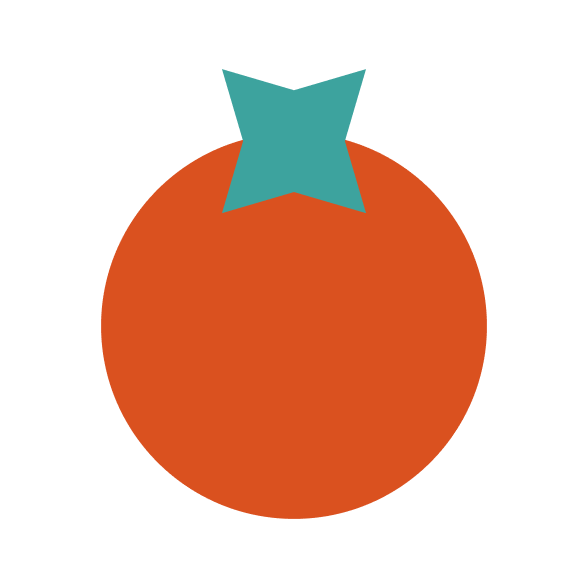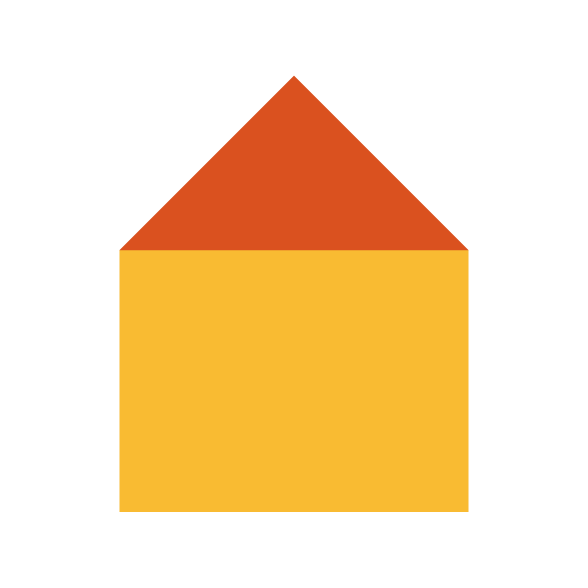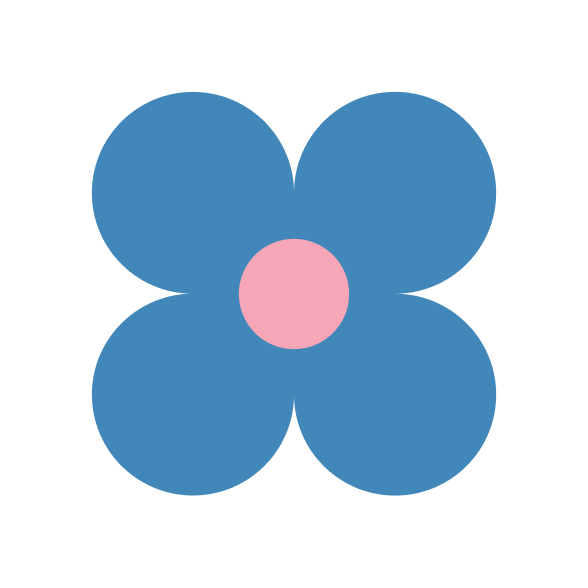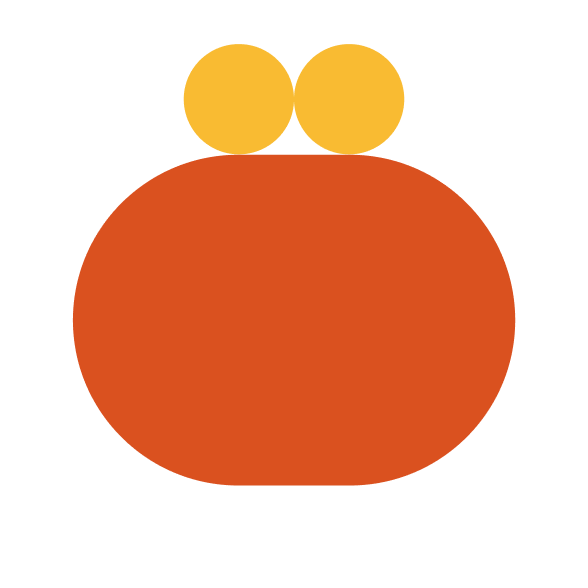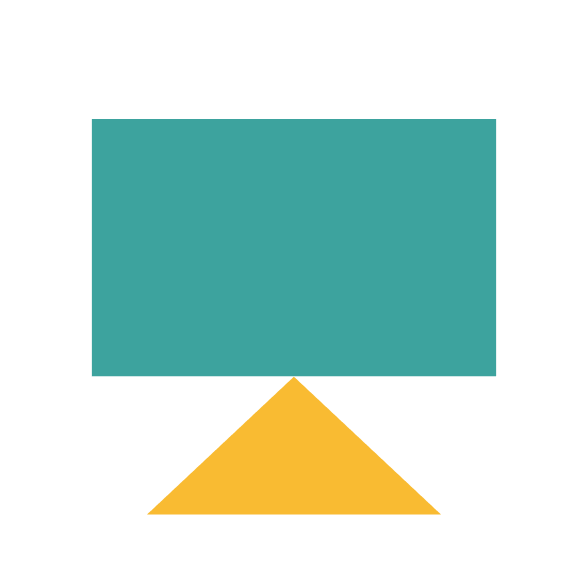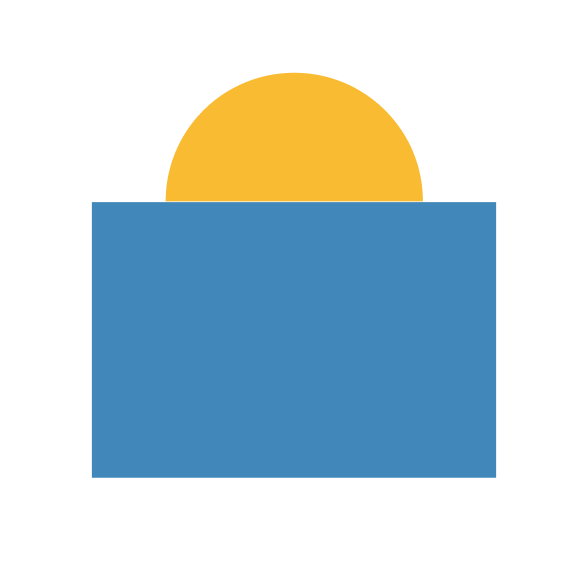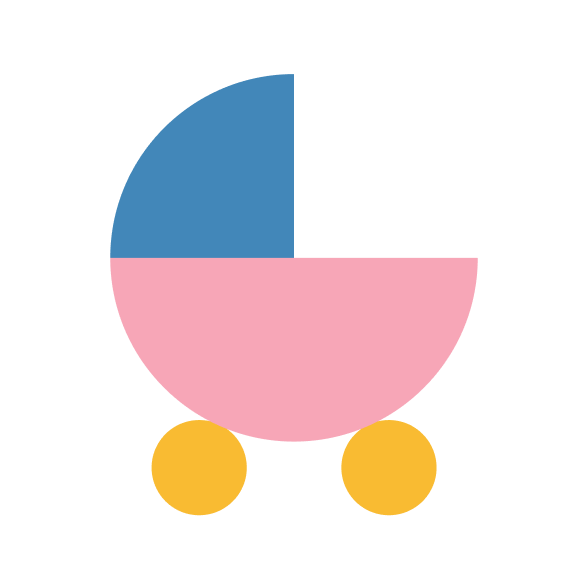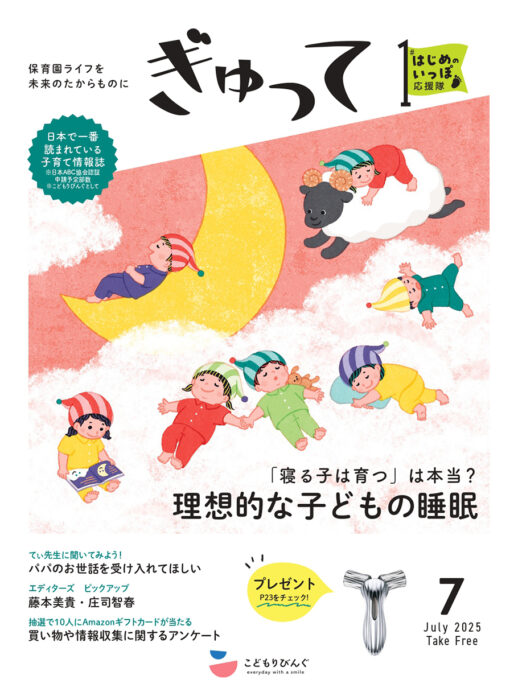更新 :
下の子を優先しがちな人は要注意!対応の差が大きな心の傷になることも

2人以上のきょうだいで、下の子が生まれると、どうしても下の子に手がかかり上の子をおろそかにしてしまいがち。また、いわゆる「上の子かわいくない症候群」が発生し、いけないと思いつつも下の子を優先してしまうということもあるようです。
実はこの「下の子ばかり手をかける」という状況が、上の子の心の傷になり、人格形成に影響を与えることもあるので注意したいところ。
今回は心理カウンセラーの立場から、下の子に手をかけすぎてしまったために起こる弊害と、親が心がけたいこと、親からのNGワードなどを紹介します。

親が下の子ばかり…大人まで続く「弊害」
親が下の子ばかりを気に掛けていた、という人が大人になっても抱えがちな弊害には、どんなものがあるのでしょうか?
自己肯定感をもてない
「自分よりも下の子が優遇されていた」と感じている人の中には、大人になるまで自己肯定感をもてずに苦労するケースが多く見られます。親に価値を認めてもらえなかったと感じることで、自分には価値がないように思え、その穴を埋められないまま大人になってしまうのです。
人からの愛情を疑ってしまう
自己肯定感が低いので、友情や恋愛において誰かから愛された時も、その愛情を疑ってしまうことが多いようです。これは自己嫌悪を招きますし、相手との関係がうまくいかないことにもつながります。
人から評価されるように振る舞ってしまう
常に相手に喜ばれるように、自分の本心は二の次にして頑張ってしまいます。相手にとって価値のあるものを提供できなければ、自分の価値がない、好いてもらえないと考えるための行動です。心の病の原因になることもあります。
弟や妹との関係がぎくしゃくしてしまう
年齢がいくつになっても、弟や妹に対して抱いた嫉妬や、理不尽さといった気持ちが完全に消えることはありません。親に原因があるとわかっていても、本心からお互いを想い合う大人同士になれないことは、親にとっても理想的ではないのでは…。
ココ気をつけて!親が避けるべきNGワード・シチュエーション
親自身がいくつかの言動に気をつければ、上の子に過剰な負担をかけず、下の子に優しくしてくれるような環境を作ることが可能です。親が気をつけたいことをまとめました。
要領がよい下の子だけ褒めるのはNG!
下の子は、上の子のあれこれを見て育つので、成長が早く要領がよいことが多いものです。親はついつい「上の子よりも早くできるようになった」「上の子は遅かったけど、下の子は要領がよい」なんて言ってしまいがち。
しかし、下の子が素早くできるのは、上の子を見て流れを把握しているからです。ですから「お兄ちゃん(お姉ちゃん)を見ているおかげで、弟(妹)がしっかりできるようになった」とするのが正解! 上の子も自信がもて、下の子の手本になろうと、自ら努力するようになります。
きょうだいゲンカでは上の子のケアを忘れずに
きょうだいゲンカは、兄弟姉妹がいれば日常茶飯事です。原因は必ずしも上の子ではないのですが、さまざまな事情で親がつい上の子を怒ってしまうことも。「お兄ちゃん(お姉ちゃん)なのに、どうしてガマンできないの?」「折れてあげなさい」なんて言われてイヤな思いをした経験者もたくさんいるはず!
どちらの言い分も落ち着いてしっかりヒアリングをし、どちらの何がいけなかったのか平等に判断した上で、落ち着いて言い聞かせることが大切です。特に下の子が幼く言い聞かせても分からない年齢の場合、上の子は理不尽な気持ちでいっぱいです。下の子をかばうのではなく、上の子の気持ちに寄り添った対応を心がけましょう。
上の子だけを怒っていないか要チェック
上の子は親にとって初めての育児。しっかり育てなければという思いから「片づけなさい!」「勉強しなさい!」と怒りっぱなしになることも。一方下の子は、一度上の子が通り抜けた道ですから「上の子が幼稚園の時も、片づけはできなかったな」なんて思ってしまい、ついつい怒らずにスルー…。これでは上の子にとって、自分だけがいつも怒られている状況が続くことになってしまいます。
子どもは怒られることでやる気が起こることはなく、反発心を強めるばかりです。その結果、ほめられて育った弟や妹のほうが学業で伸びるケースも多く、やがて進学先に差が出て劣等感の要因になったりすることも。
上の子に厳しくなるのは、上の子に対する期待から起こることではありますが、「子どもが伸びるのは怒られるときではない」ということを意識して、目的に合った親の対応を冷静に考えるべきでしょう。
きょうだい仲は親が思うよりも複雑、幼いからこそ真剣に向き合って
大人になってきょうだい仲に疑問をもつ人に話を聞くと、わだかまりの根本は幼少期にあることがほとんど。親はそのときそのときで必死に考えて育てているつもりでも、留意するポイントを間違えると大きな心の傷になります。
大人の考える「正しさ」よりも、まずは子どもの「気持ち」を考えること。そして、幼いからこそ真剣に向き合うこと。それこそが幼少期育児には必要なのだと感じています。